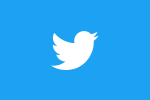賃貸で鍵を紛失したときの正しい対処法と費用負担のポイント
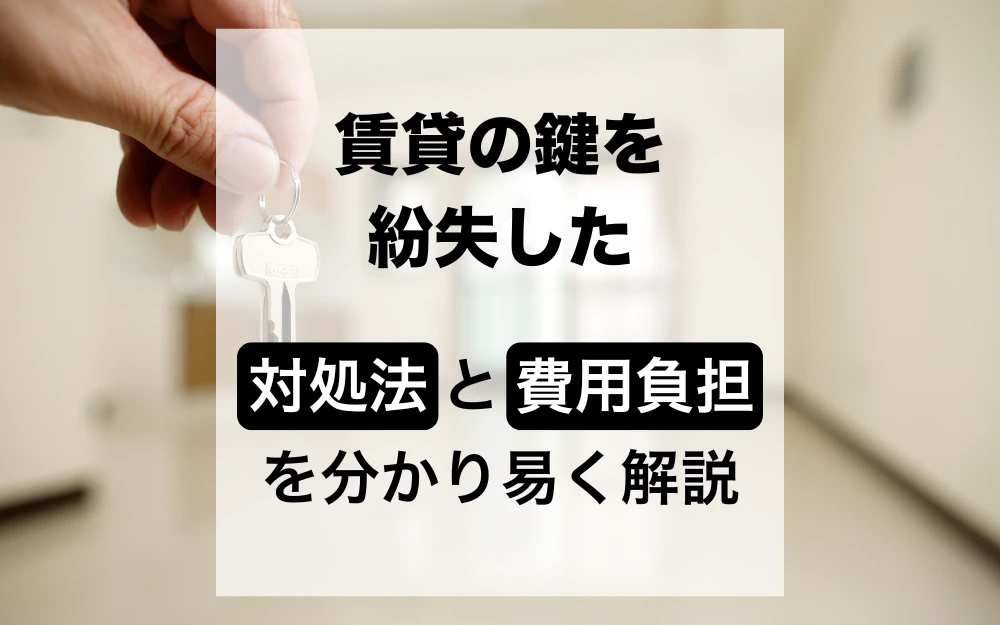
【目次】
ふと気づいたら鍵がない…そんなとき、焦りと不安で頭が真っ白になってしまいますよね。
「賃貸マンションの鍵をなくしてしまった!」という状況は誰にでも起こり得るトラブルですが、落ち着いて対処すれば大事に至らず解決できます。
まずは、この記事の結論である「最優先でやるべきこと」と「かかる費用の目安」を一覧表にまとめました。今すぐ何をすべきか確認したい方は、こちらをチェックしてください。
【結論】鍵紛失時の緊急チェックリスト
| 項目 | 具体的なアクション | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 探す | 立ち寄った場所、カバン・服の全ポケットを確認 | 意外と手近な場所にあることも。大部分はここで鍵が見つかる。 |
| 2. 届ける | 最寄りの警察署・交番へ「遺失届」を出す | 電話やネットで届出可能な自治体もあり。 |
| 3. 伝える | 管理会社・大家さんへ連絡する | 24時間窓口や合鍵の有無を確認 |
| 4. 開ける | 管理会社の指示を受け、鍵業者を手配 | 火災保険や緊急駆けつけサービスが使えるか確認。連絡取れない場合は鍵開けのみ鍵屋に依頼し、鍵交換は管理会社の指示に従う |
費用負担の目安
| 項目 | 費用相場 | 負担者 |
|---|---|---|
| 鍵開け(解錠) | 15,000円 〜 35,000円 | 自己負担(保険で無料の可能性あり) |
| 鍵交換 | 15,000円 〜 35,000円 | 原則自己負担(入居者の過失時) |
以下では、各ステップの詳細な進め方や、退去時の注意点、二度と鍵をなくさないための対策までを順を追って解説します。
※この記事は、賃貸物件にお住まいの方向けです。
持ち家での方は、「家に入れない!家の鍵が無い時の4ステップ対処法」の記事をご覧ください。
まずやるべき初期対応
鍵を紛失に気づいたら、パニックになる気持ちをぐっと抑え、以下のステップで初期対応を行いましょう。
迅速かつ的確な行動が、後の不安を減らすカギになります。
落ち着いて周囲を探す

まず深呼吸して気持ちを落ち着け、最後に鍵を使った場所や立ち寄った場所を思い出しましょう。
服のポケットやカバンの中、車内など身の回りをもう一度丁寧に確認します。
意外な所からひょっこり出てくるケースも少なくありません。
「絶対にここに入れたはず」と決めつけず、部屋の中や玄関周辺も含め広範囲に探してみてください。
警察署・交番に遺失届を提出する
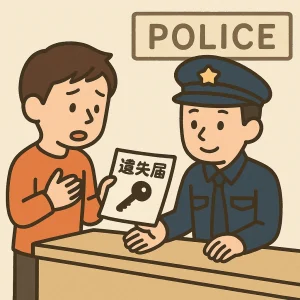
探しても見つからない場合は、最寄りの警察署や交番に鍵の紛失届(遺失物届)を出しましょう。
誰かが拾って届けてくれている可能性もありますし、後日見つかった際に連絡を受けられます。
また、悪意のある第三者が拾った場合の犯罪悪用を防ぐためにも、公的に紛失を記録しておくことが重要です。
深夜で直接行けない場合は電話連絡でも受け付けてもらえることがあります。
警察への届け出は防犯と発見の両面でメリットがあるので、必ず行いましょう。
管理会社や大家にすぐ連絡する

次に、賃貸物件の管理会社または大家さんに鍵を紛失した旨を連絡します。
賃貸契約者として報告は義務と言えますし、鍵を開けてもらう助けを得られる可能性もあります。
管理会社によっては24時間対応サービスがあり、担当者がスペアキーを持って駆け付けてくれることもあります。
大家さん直営物件の場合でも、近隣に住んでいれば合鍵を持って来てもらえるかもしれません。
「夜遅いから…」と遠慮せず、緊急時なので時間帯を問わず連絡しましょう。
連絡の際は「〇号室の○○です。鍵を紛失してしまい部屋に入れません」と簡潔に状況を伝えるとスムーズです。
必要に応じて鍵の専門業者を手配する

管理会社や大家さんから指示を仰ぎ、必要であれば鍵屋に解錠を依頼します。
管理会社側で業者を手配してくれる場合もありますし、自分で信頼できる鍵屋さんにお願いすることも可能です。
特に深夜や早朝で管理会社が対応できない場合は、24時間対応の鍵業者に直接連絡して来てもらう方が早いでしょう。
依頼時には住所・建物名・部屋番号、鍵の種類など聞かれるので分かる範囲で伝えてください。
業者に開錠してもらう際は、賃貸契約者本人であることを示す身分証の提示が求められます。
無事室内に入れたら、後述する今後の対応(鍵交換の要否など)について管理会社と相談しましょう。
以上が初期対応の基本ステップです。
ポイントは「落としたかも」と思った場所を冷静に洗い出すことと、然るべき機関へ迅速に連絡することです。
早めに手を打てば鍵が見つかる可能性も高まりますし、防犯対策にもつながります。
鍵紛失の費用相場は?火災保険は使える?

鍵を紛失すると、鍵を開けるところから新しい鍵への交換まで何かと費用がかかります。
ここでは鍵開錠と鍵交換それぞれの費用相場と、その費用負担は誰がするのか説明します。
また、火災保険などで使えるサポートがあるかも併せて確認しましょう。
鍵開けを業者に依頼した場合の費用
鍵をなくした際にまず直面するのが、閉まったドアを開ける鍵開け作業です。
鍵業者に鍵開けを依頼した場合の費用相場は、鍵の種類や現場状況によって変わりますが15,000円〜35,000円程度です。
一般的なシリンダー錠であれば業者到着後15〜30分ほどで解錠でき、そのくらいの料金になるケースが多いようです。
ただし夜間・早朝など時間外対応の場合は割増料金や出張費が加算され、1.5〜2倍程度になることもあります。
緊急時には多少高くても開けてもらうしかありませんが、業者に頼む際は電話でおおよその見積もりを確認しておくと安心です。
なお、鍵開け費用は基本的に紛失した本人の負担です。
鍵をなくしたのは借主側の過失ですので、管理会社や大家さんが費用を負担してくれることはまずありません。
現場で業者に現金支払いやクレジットカード払いが一般的です。
領収証は後で保険請求する際に必要になる場合もあるので受け取っておきましょう。
鍵の交換にかかる費用と負担
鍵開け後、紛失した鍵が見つからなければ防犯のため鍵そのものを交換することを強くおすすめします。
特に鍵と一緒に住所や部屋番号が分かるものを紛失した場合、誰かに拾われて悪用されるリスクが高まります。
鍵だけの場合でも所在が特定されない保証はないため、心配であれば交換すべきです。
鍵の交換費用は先述のとおり鍵の種類によって幅がありますが、賃貸で多く使われるピンシリンダーなら15,000〜25,000円程度、ディンプルキーなら25,000〜35,000円程度が目安です(防犯性が高い特殊キーはもっと高額になる場合あり)。
交換作業も鍵業者が行い、作業代+部品代の合計金額となります。
作業時間は1ヶ所あたり30分〜1時間ほどです。
この鍵交換費用も基本的には紛失した入居者の自己負担となります。紛失は入居者の過失によるものなので、貸主が負担する理由がないためです。
管理会社に鍵交換を依頼した場合でも、後日請求されるか敷金から差し引かれるのが通常です。
例外は、鍵が盗難に遭ったなど明らかに第三者の犯罪被害による場合ですが、その場合もまずは入居者側で費用を立て替え、後から保険金で補填する流れになります。
賃貸物件の鍵交換については「賃貸物件の鍵交換の費用は借主が負担する?知ると得する費用に関する知識」でも詳細をご紹介しています。
火災保険や保証サービスで補償される?

鍵の紛失トラブルに関連して、「加入している火災保険で何か補償を受けられないか?」と考える方もいるでしょう。
実は近年、火災保険や住宅総合保険の特約で鍵の紛失時に役立つサービスが付帯していることがあります。
代表的なのは「緊急駆けつけサービス」といった名称で、契約者が鍵を紛失した際に専門業者を派遣して30分程度の開錠作業を無料で行ってくれるというものです。
多くの保険会社ではこの無料開錠サービスを年1回利用可能な付帯サービスとして提供しています。
通常の鍵であれば30分以内に開けられるケースが多いため、保険に入っていれば実質タダで玄関を開けてもらえることになります。
ただし注意したいのは、すべての火災保険にこのサービスが付いているわけではない点です。
契約プランによって有無が分かれるので、自分の保険証券や加入時のパンフレットを確認しましょう。
もし付帯サービスが無ければ、鍵業者への支払いは自己負担になります。
また、サービスがあっても鍵開け以外(鍵交換作業や作業超過分)は有料となるケースがほとんどです。
たとえば高性能なディンプルキーで30分以上かかった場合、その超過分費用や部品代は自己負担になります。
一方、鍵の交換費用自体を保険金で補償してもらえるケースは限定的です。
基本的に「鍵の紛失」は保険の補償対象外であることが多く、盗難被害で鍵を破壊された場合などに限って保険金が出る商品もあります。
一部の火災保険ではオプション特約で「盗難に遭い鍵を交換した費用」を補償するものもありますが、単なる紛失で鍵交換した費用は自己負担となるのが一般的です。
以上をまとめると、保険で期待できるのは開錠サービスと思っておいた方が良いでしょう。
鍵をなくしてしまったら、まず自身の加入保険にそういったサービスがないか確認し、あれば遠慮なく依頼しましょう。
ない場合は費用はかかりますが、自費で速やかに開錠・交換するのが安全です。
退去時に鍵が見つからない場合の注意点

鍵を紛失したまま賃貸物件の退去日が近づいている場合は、いくつか注意すべきポイントがあります。
退去時には貸主への鍵の返却が義務付けられていますが、返却すべき鍵をなくしてしまった場合、基本的に借主負担で鍵の交換を行う必要があります。
具体的には、退去立ち会い時に鍵が足りないことが判明すると、貸主側でシリンダー交換等の措置をとり、その費用を敷金から差し引くか後日精算する形となります。
事前に鍵を紛失していると分かっている場合は、退去日を待たずに早めに管理会社へ相談しましょう。
黙っていても最終的にバレて費用請求されるだけでなく、防犯上も次の入居者に迷惑がかかります。
管理会社に連絡すれば、退去日までに借主側で鍵交換を手配すべきか、それとも貸主側で交換して費用請求するかなど指示を受けられるはずです。
指示に従い適切に対処しましょう。
万一本当に直前になって鍵紛失が判明した場合でも、決して自己判断でこっそり鍵穴を交換したり合鍵を作って埋め合わせたりしないでください。
述べられているように、退去後に無断で鍵を変更・増設していたことが発覚するとトラブルになります。
最悪の場合、無断侵入の意図を疑われる恐れもあります。
必ず管理会社の指示のもとで処理するようにしましょう。
費用面では、鍵紛失による交換費用は前述のとおり借主負担です。
鍵の種類によって交換費用は1万円〜場合によっては10万円程度と幅がありますが、特殊な高級鍵でない限りは数万円程度で済むケースが大半です。
契約書に鍵紛失時のペナルティや保険について記載があれば、その内容にも従う必要があります。
例えば「紛失時は一律○万円を支払う」と定められていればその金額を支払いますし、鍵紛失補償の特約があれば保険金でまかなえる可能性もあります。
いずれにしても、退去時までに見つからない鍵は戻ってこないものと割り切り、速やかに費用を負担して次に進む方が賢明です。
なお、退去後に偶然鍵が見つかったとしても、交換済みであれば元の鍵は使えませんし返金も基本ありません。
落とし物として警察から返却された場合でも同様です。
ですから、「いつか出てくるかも…」と先延ばしにせず、見つからなければ新しい鍵で次の生活を始めるほうが安全と言えるでしょう。
二度と鍵をなくさないためにできること(紛失防止グッズ・習慣)
今回の紛失を教訓に、今後は鍵をなくさないための対策を講じましょう。
以下に鍵の紛失防止に役立つグッズや習慣を紹介します。
目立つキーホルダーを付ける
鍵単体だと小さくて目に留まりにくいですが、大きめで色鮮やかなキーホルダーを付ければ視認性が上がり紛失リスクを減らせます。
触ったとき存在に気づきやすくするため、手触りの特徴的なものを選ぶのも効果的です。
また、鈴付きのキーホルダーなら移動のたび音が鳴って存在を思い出させてくれます。
伸縮リールキーを活用する
伸びるワイヤーが付いたリール式キーホルダーをバッグやベルトに装着し、鍵を使うとき以外は自動的に定位置に戻るようにしておきます。
これにより、鍵を一時的にどこかに置いてそのまま忘れるといった事態を防げます。特に外出先で鍵を取り出す機会が多い人に有効な方法です。
Bluetoothトラッカーを取り付ける
スマートフォンと連携できる紛失防止タグ(キーファインダー)を鍵に付けておくのも現代的で効果的な対策です。
鍵を見失ったときにスマホアプリから発信音を鳴らしたり、最後に検知した場所を地図表示したりできます。
代表的なものに「MAMORIO」や「Tile」「AppleのAirTag」などがあり、小型でキーホルダー感覚で付けられます。
多少のコストはかかりますが、貴重な鍵を探し出す手間と安心感を考えれば検討する価値があります。
鍵の定位置を決め習慣化する
家の中で鍵をどこに置いたか分からなくなる人は、玄関に鍵掛けを設置するなどして必ず決まった場所に置く習慣をつけましょう。
「家に帰ったら玄関のフックにかける」「出かける前に指差し確認する」などルール化すると、鍵の所在管理がぐっと楽になります。
毎日の習慣が最大の紛失防止策です。
個人情報の書かれたタグを付けない
鍵に住所・部屋番号・氏名などの情報を書いたタグを付けていると、落としたときに第三者に住居を特定される恐れがあります。
防犯上きわめて危険です。
鍵には必要以上の情報を持たせず、どうしても連絡先を書きたい場合は携帯番号程度に留めましょう。
これらの対策を組み合わせれば、鍵を紛失するリスクは大きく下げられます。
「鍵はここ」「使ったら戻す」という意識を常に持ち、便利グッズも活用しながら再発防止に努めてください。
まとめ(冷静に対応を進めよう)
鍵をなくしてしまった直後は不安でいっぱいになるものですが、冷静な対処こそが問題解決への近道です。
まずは落ち着いて探し、警察や管理会社に連絡する適切なステップを踏めば、大きなトラブルになる前に対応できます。
費用はかかるかもしれませんが、鍵開けや交換も専門家の力を借りればスムーズに進みます。
そして今回の出来事を踏まえて紛失防止策を講じておけば、今後は安心して生活できるでしょう。
鍵を紛失したときこそ慌てずに本記事の内容を思い出し、順序立てて対応を進めてください。
冷静な行動と準備で、きっと不安は解消されるはずです。
鍵の問題を乗り越えて、どうかこれからも安全・安心な毎日をお過ごしください。
User Review
( votes)藤原 正徳
最新記事 by 藤原 正徳 (全て見る)
- ドアバー・ドアチェーンは無意味?玄関防犯の勘違いとプロが教える限界 - 12月 28, 2025
- 【カギ開け】ピッキングのやり方!どういった鍵が開けられるのか - 12月 14, 2025
- 鍵屋の高額請求・ぼったくり手口を全公開!レスキュー商法から身を守る「依頼前の鉄則」 - 11月 29, 2025
記事が参考になりましたら、シェアしていただけると嬉しいです!